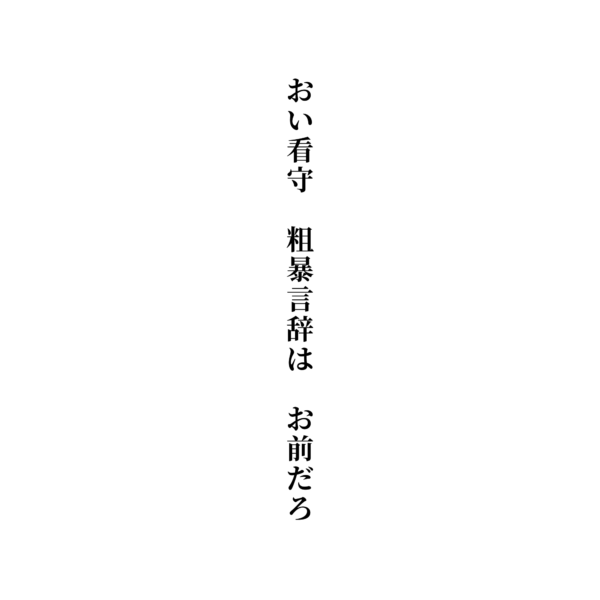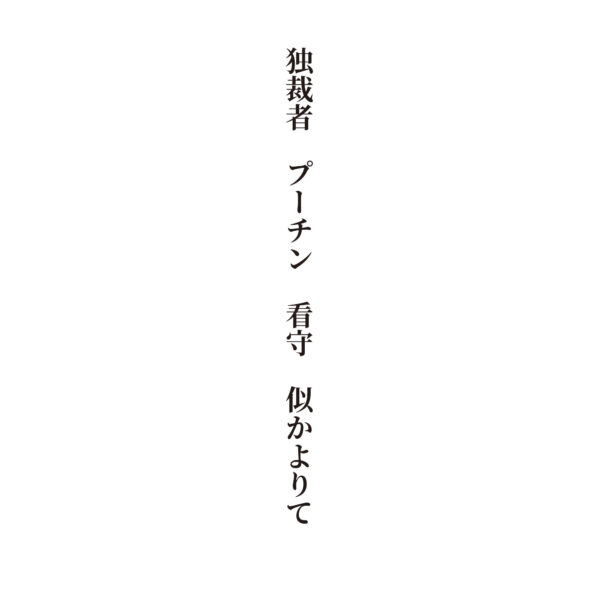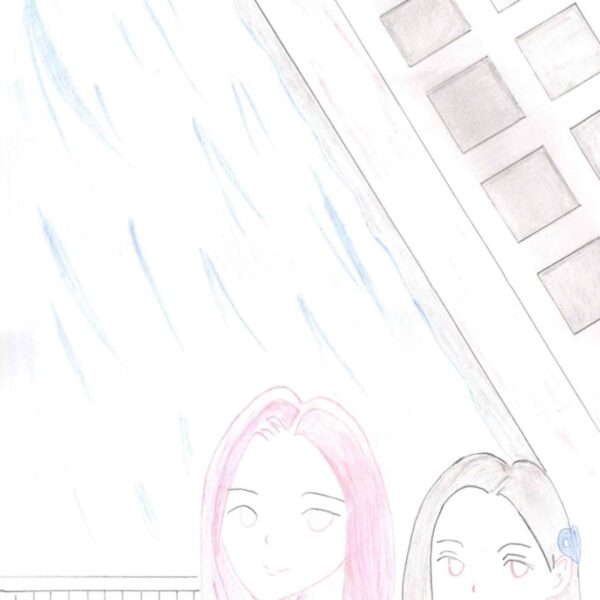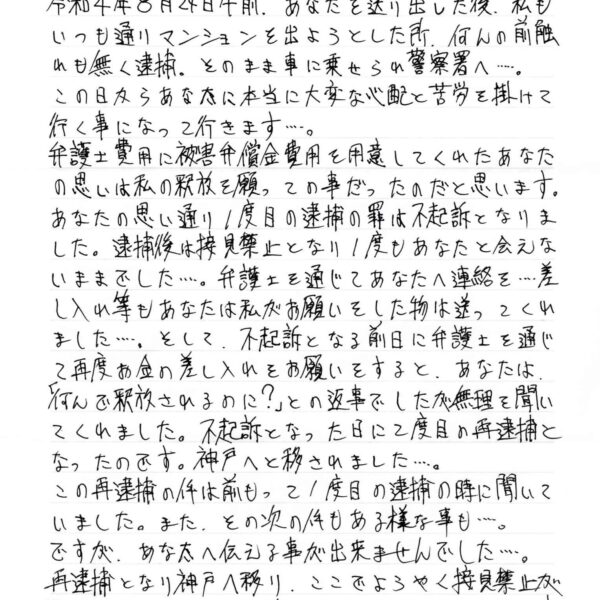作品タイトル
くまさんの魔法のクスリ
作者
くま
作品本文
私が唯⼀、両親から⾔われていたことは「⼤学に⼊りなさい」ということだけだった。
「男だったら⼤学くらい⼊ってないと、どうしようもない」
幼少期から私はこんなセリフを、お盆やお正⽉に⺟や⽗の実家に帰る度に、⽿にしていた記憶がある。そのせいか、私の無意識には⼤学に⼊ることがインストールされていたように思う。
私は両親の⾔葉通り⼤学⽣になってやった。ところが、「⼤学で何をやりたい」とか特に何も考えていなかったことと、周囲との⽐較による劣等感から⼤学に⾏くのが、苦痛になってしまった。そんな私を⼤学がある駅まで向かわせたのは、⼀軒の⿇雀屋だった。私は⼤学に⾏く振りをして、その店に⼊り浸り、ついにはそこでバイトをするようになった。そして私はその店で、私より偏差値の⾼い有名国⽴⼤学に通う2つ年上のドレッドーヘアーの男から、魔法のクスリを教わった。
「クリスタルって⾔って、イギリスの学者もやっているから、⼤丈夫」
ドレッドヘアーはそう⾔って私に魔法のクスリを勧めてきた。アルミホイルの上にクリスタルを置き、ライターを弱⽕にしてアルミホイルを下から炙り、気化した煙を、正⽅形の付箋をまるめてストローにしたもので、できるだけたくさん体内に吸い込み、息を⽌める。
「何これ?すごい。頭がスッキリする」
私はすぐに魔法のクスリの虜になった。そして私の魔法のクスリ遊びは、それから9か⽉程続いたが、魔法のクスリで遊ぶことを簡単に辞めることができた。
「なんだ、簡単にやめられるじゃん。」
幼少期にテレビCMで観た、「⼈間辞めますか?」というキャッチフレーズは嘘っぱちであると思った。
ところが、魔法のクスリはそんなに⽢いものではなかった。⼀度魔法にかかると、その魔法は少しずつ⼒を持ち、魔法にかかっていることをほとんどの⼈は気づくことができない。それが魔法のクスリの本当の意味での魔法なのである。それはまるで、新横浜を発⾞してひと眠りすると名古屋に到着する、東海道新幹線の「のぞみ号」のようなものだった。⾃分が魔法にかかっていることに気づくためには、時速200キロを超える電⾞から⾶び降りるくらいの覚悟が必要だ。ほとんどの⼈はそんな勇気はない。28歳の時には、私は名古屋駅の⼿前にいた。その年に私は7⼈のむじん君という魔法クスリの⼿先から、275万円の借⼊をした。魔法のクスリを使うために。私は30歳のある⽇、魔法のクスリ売っている⽸ビール持ったおじさんに⾔った。
「このバイト楽ですか?」
「楽だよ。それに、魔法のクスリを皆に教えてあげる素敵な仕事だよ」
そして、次の⽇から、魔法のクスリを毎⽇20⼈くらいの私と同じように魔法のクスリの虜になっている⼈に届けた。そして、30歳夏に、私は名古屋駅に到着した。牢屋の中だった。⾵の噂で、魔法のクスリの虜になると、牢屋に⼊ることは聴いたことがあったが、あくまでも噂だと思っていた。しかし、噂ではなかった。30歳の暮れに、
「被告⼈を懲役2年6⽉、罰⾦30万に処する」
と裁判官は私に告げた。
そして⼿錠をかけられた私は、東京から新幹線のヒカリ号に乗り、私を含め6⼈の囚⼈と縄で繋がれ、3⼈の刑務官に連れられて、名古屋駅で降りた。そこからJR電⾞に乗って、三重県の津市にある、刑務所に移送された。この刑務所では刑務官のことを先⽣と呼ぶ。
「先⽣、458番、腹痛のため⽤便願います」
どうやらここでは、何かする時は必ず先⽣の許可がいるようだ。そして、⽬を覆いたくなるようなたくさんのルールがあり、ここで快適に過ごすためには、先⽣に対して従順であることが不可⽋であった。私は幼い頃から、先⽣に好かれるのは得意であった。だから、この空間で過ごすことは私には、それほど難しいことではなかった。つまり、良い⼦はここでは重宝されるのである。
良い⼦の私は刑期より、7⽉早く⾃由の⾝となり、良い⼦の私は仕事に就いた。そして、魔法のクスリは悪い⼦がやることだと⾝体で覚えた。もう、刑務所は嫌だった。しかし、魔法のクスリから呪縛からは簡単に逃れることができなかった。私はある⽇、また魔法を使いたくなった。嫌なこと全て引き受けてくれる魔法のクスリ。⾃由の⾝となってから3年を迎えようとしていた頃には、私は魔法を使わないと仕事ができなくなっていた。そして、気が付くと、私は7つの罪で裁判を受けていた。
「被告⼈を懲役2年6⽉に処する」
裁判官はさらに続けた。
「あなた、魔法のクスリはもう辞めなさい」
「辞めなさいの⼀⾔で、辞められるなら、魔法じゃないよね。裁判官は魔法にかかったこともないくせに」
と私は⼼の中で毒づいた。
良い⼦の私は、また5⽉ほど早く⾃由の⾝となった。だが魔法の解き⽅については知らないままだったので、今までどおり、魔法を使いながら、仕事をした。私は焦った。
「このままじゃ、また刑務所に⾏く」
そんなある⽇、私は魔法のクスリを使っても恐くて、仕事に⾏けなくなった。どうやら、私は魔法に依りすぎたので、魔法が効かない⾝体になったらしい。それから2⽉経ったある⽇のことである。深夜に突然、過去に経験したことのないようなパニックが私の⼼と⾝体を襲った。私はとにかく落ち着きたくて、⼿元にあった魔法のクスリを使ったが、全く効かなかった。私はなんとかパニック収めようと、床に置いてあった1冊の本を斜めに読んでいった。その本の感情について詳しく書かれていた箇所で私の⽬が⽌まった。⽬から鱗が出た。
⼈は⻑い間、感情を抑えると感情⾃体が⿇痺するそうだ。そして、感情にはネガティブな感情とポジティブな感情があり、ネガティブな感情を抑制すると、ポジティブな感情も抑制され、何をやっても楽しめなくなり、喜べなくなるらしい。
「ん?そう⾔えば、魔法のクスリって嫌なことがあった時に、その感情を味わいたくないから使っていたな。そういうことだったのか。」
⽣きていることが楽しくないから魔法のクスリを使う、すると感情⿇痺が強化される。つまらないから、また魔法のクスリと使う。「そっか。私は⾃ら感情を⿇痺させ、ただ不幸の無限ループをしていたのだけだったのか。」
それから、6年が経つ。私は今、シラフで感情をありのままに感じるという別の魔法を使いながら少し幸せに⽣きている。
作品ジャンル
小説
展示年
2024
応募部門
自由作品部門
作品説明
20歳の時に薬物を覚え、30歳から2度の服役をして、37歳で薬物をやめるまでのプロセスを小説にしてみました。小説を書くのは初挑戦で、小説になっているか微妙ですが、読んでいただけたら嬉しいです。読み返していると、何度も表現を変えた方が良いのではという部分があって、小説を書くのは大変なことだと思いました。同時に色んな表現ができる自分を「もしかして才能があるのかも」なんて思ったりしました。今回の作品を通して、より多くの人に依存症について知っていただけたらと思っています。