「刑務所アート」とは、刑務所で服役する受刑者の作品を中心とする、刑務所という環境下で、また刑務所という制度とかかわる人たちによって生み出される芸術表現活動です。
私たちPrison Arts Connections(PAC)は、「刑務所アート展」の企画・運営を中心に、刑務所の内と外、被害と加害を越えた対話と回復の契機を生み出す活動に取り組んでいます。
みなさんは、「刑務所」とはどんな場所だと思いますか?
「受刑者」と聞いて、いったいどのような人々をイメージしますか?
罪を犯し、法のもとに裁かれ、刑務所で服役する人たちは、もちろんその行為に対する償い・更生の責任を負うことになりますが、私たちと同じ一人の人間であり、刑務所に入るに至った経緯や背景もさまざまです。服役中の日々、どんなことを考え、誰に何を伝えたいと思い、どんな表現をするかも、もちろん、受刑者一人ひとり異なります。刑期を終えて出所した後にも、一人ひとり違った人生が待っています。
しかし、刑務所という、制度的・物理的な「壁」によって、また、罪を犯した人に対する差別や偏見といった心理的な「壁」によって、お互いの姿が見えにくくなっていると思います。
アートには、こうした「壁」を越えてさまざまな人々をつなぎ、司法の場やマスメディアとは異なる仕方で、犯罪やその回復をめぐるコミュニケーションを可能にする力があります。
一人ひとりの受刑者にとって、表現行為がどんな意味を持つのか。刑務所の中の表現環境とはどのようなものなのか。加害者家族・被害者家族はどのような思いを抱え、双方に現状どのような支援や課題があるのか。加害/被害を超えた対話の可能性はあるのか。単に受刑者の作品を集めて展示するだけではなく、作品の募集から展示に至るプロセスで、こうしたさまざまなテーマについて、当事者・支援者・研究者で対話を重ねてきました。
作品を通して生まれるコミュニケーションが、受刑者にとっては社会とのつながりを感じる契機となり、塀の外にいる私たちにとっても、刑務所やそこに生きる人々について想像を巡らす機会になると考え、刑務所アート展を開催しています。
アートは再犯率を低下させる?
アメリカやヨーロッパでは、刑務所でアート・プログラムを行うことは珍しくなく、専門的な非営利組織も多くあります。
かの有名な刑務所映画の名作『ショーシャンクの空に』の主役であった俳優のティム・ロビンスは、実際の刑務所で演劇のワークショップを行う活動 「Actors’ Gang Prison Project」を行っています。再犯率の低下や違反行為の減少などの効果も指摘されています。
アートプログラムが、再犯を防ぐ、犯罪からの離脱を促す効果があるといった実証研究は多く存在します。日本でこうした活動を広げていく上でも、この「再犯防止」という効果が、一つの説得材料になり得るかもしれません。
刑務作業が必須でなくなる「新たな拘禁刑」が議論されている現在、日本でもアート・プログラムが教育として取り組まれる可能性はゼロではありません。実際、少年院においては情操教育として表現活動が行われる例は少なくありません。
しかし、それだけではなく、私たちはアートの「つなぐ」という役割についても考えてきました。
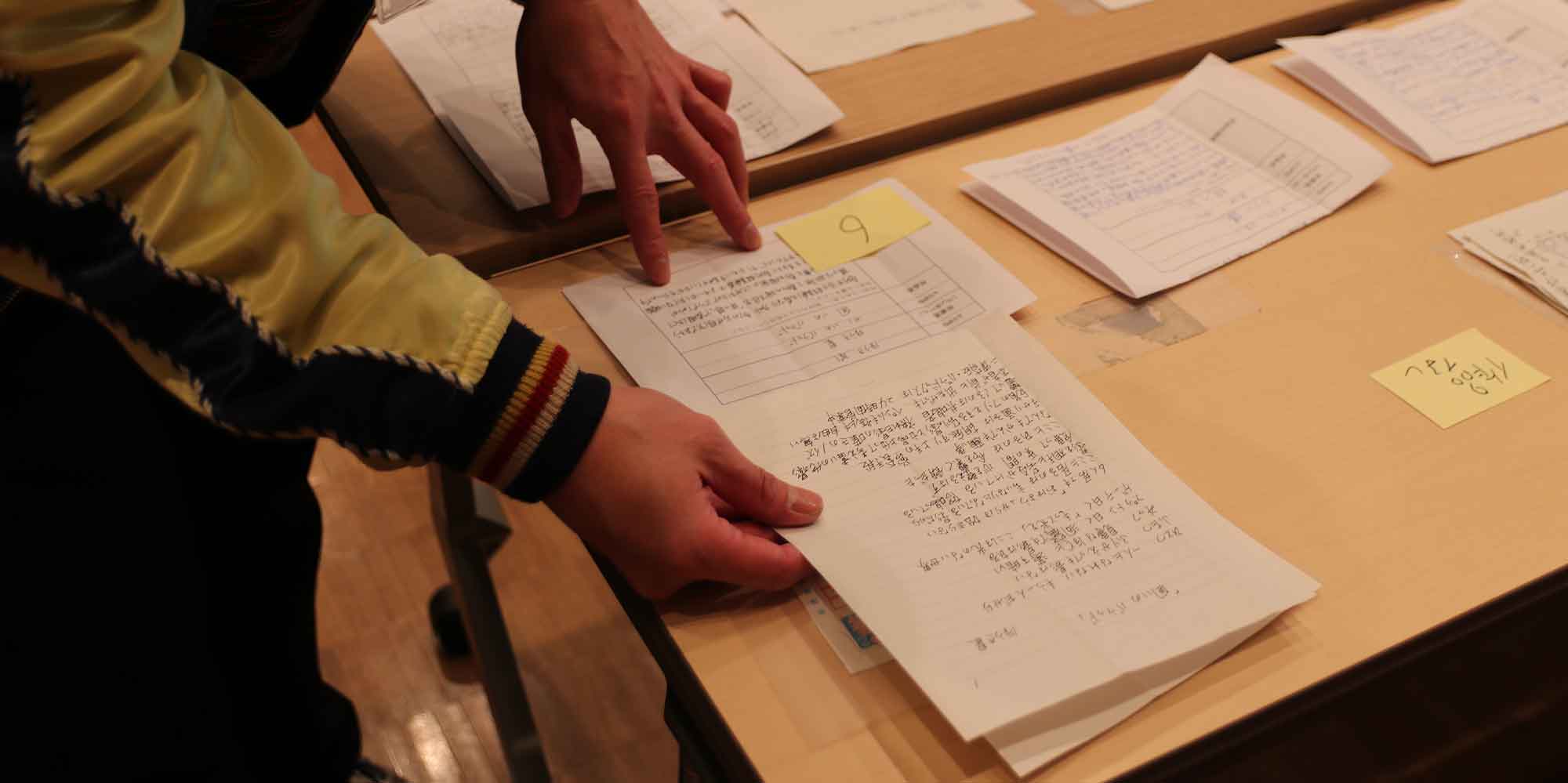
アートが、塀を越えた「対話」の媒介となる
私たちPACが活動のモデルとしたのは、イギリスの慈善団体Koestler Arts(ケストラー・アーツ)です。この団体は、Koestler Awardというイギリス全土の被収容者を対象とした大規模な公募展を毎年開催しています。
もう60年もの歴史があるのが驚きです。またその規模も大きく、毎年イギリス全土の3,500人以上の応募者から、7,000以上の作品のエントリーがあります。応募作品には、約100人の専門の審査員によって約2,000もの賞が授与され、イギリス最大の芸術センターであるサウスバンクセンターに展示されます。
Koestler Artsがこの取り組みにおいて重視しているのは、応募作品への「フィードバック」だといいます。日本でも行われている文芸作品コンクールは、受刑者から応募された作品に対して銅賞・銀賞・金賞という賞を用意し、受賞者には選評も送られているようですが、Koestler Artsは受賞作品に限らず応募作品の95%に対してフィードバックを返しています。表現は、誰かとのコミュニケーションとなって初めて意味をもつと考えているからです。
2010年には、犯罪の被害者グループが受刑者の作品をキュレーションして展示をつくるという取り組みも行われました。サウスバンクセンターの専門家によるレクチャーで、被害者の方にキュレーションを学んでもらい、展示をつくる作品を選定していきます。
私たちも、Koestler Artsと同じく、アートを通して「対話」の場をもたらしていく過程が大切だと考えています。
発表=コミュニケーションの機会がない日本の状況
日本でも、刑務所や拘置所にいる人が表現活動に取り組む環境はあります。参加できる受刑者は非常に限られるものの、クラブ活動の中には俳句クラブや短歌クラブ、吹奏楽クラブをもつ刑務所もあります。しかし、「発表」の機会がなかなかないのが現状です。発表の機会がないということは、受刑者が自分の作品に対してフィードバックを得られない、ひいては他者の視点を取り入れる機会を得られないという課題につながります。
「京都アニメーション事件」の被告人も小説を書いていたといいます。そのことについて、犯罪学者の浜井浩一さんは次のように書いています。
刑務所では同じ服で同じものを食べる。動作時限はすべて定められ、そこでは自由も自発的行動も許されません。人として尊重されていると思う機会はほとんどありません。日本の刑罰はそれを奪うことで反省を求めるのです。「ここに二度と戻りたいと思うな。ちゃんと懲りて反省しろ」との思想が染みついています。
今回の事件の被疑者はこうした環境下で、小説を書くことで自尊感情を維持し、自分自身を保とうと努力していたのかもしれません。それ自体はポジティブなことですが…。一般論ですが、拘禁状態の中で、ひとりで創作したものに関しては、「すごくいいモノを書いた」と思い込んでしまう傾向があります。
(「踏みとどまれる社会を」京アニ事件きっかけに考える 龍谷大教授インタビュー)
拘禁状態のなか、日常においてもコミュニケーションが大きく制限される中で、ひとりでに表現活動に取り組むことは、精神の安定や自尊感情の維持に重要ですが、やはりそれが誰かに届いて反応が返ってくるという「コミュニケーション」につながらなければ、妄想がふくらむだけになってしまいかねません。コミュニケーション不全の状態で出所してきた人々を、社会にいる私たちとは異なる理解不可能な他者=犯罪者とみなして、孤立・孤独に追いつめることは、場合によっては再び罪を犯さざるを得ない状況へと追い込むことになります。
やがては社会に復帰し、同じ社会で共に生きていく(すでに共に生きている)人々だからこそ、この社会で起こった犯罪や暴力、そこからの修復や回復に社会が向き合う場を、小さくてもつくっていくことを願い、このプロジェクトを進めています。

なぜ「刑務所アート」なのか?
「受刑者アート」(あるいはアウトサイダー・アート)ではなく「刑務所アート」と呼んでいるのも、社会における刑務所という場所、制度のもとで表現があることについて想像力をもちながら考えていくためです。
アメリカでは、受刑者の過剰収容や大量投獄を問うかたちで、刑務所アートの展覧会《Marking Time: Art in the Age of Mass Incarceration》がMoMA PS1で開かれました。その展覧会の紹介を、映画『プリズン・サークル』の監督としても知られる坂上香さんが記事を書いています。
フリートウッドは、監獄アートは「アウトサイダーアート」と呼ばれることが多いが、実際にはその逆だと指摘する。「時を刻むということ 大量投獄時代におけるアート」展で展示された作品は、すべて刑罰制度と人々の関係に関わるものであり、アメリカ社会と投獄との関係を可視化していると。
「回復/修復に向かう表現 美術館で語り合う大量投獄の時代」
坂上香・ドキュメンタリー映画監督
フリートウッドは、刑務所アートが人々の関係性のうえで成り立っていることを強調します。それは、受刑者とアートプログラムの講師との関係性や、作品の素材を手にいれるための刑務官との関係(交渉)、作品を家族にギフトとして贈るといった関係性や、彼らの作品が展示され人々の間で刑務所と社会の関係性が問い直されることも含まれます。
私たちが企画する刑務所アート展でも、作品展示に加え、「刑務所アート」に関わる様々な法的・社会的制約について紹介するようにしています(刑務所による検閲、使用できる道具の制限など)。
私たちは、刑務所の中から届く表現を通して壁の向こうの人々を想像することができます。人は誰でも加害者にも被害者にもなり得て、誰かを傷つけてしまう経験、傷つけられる経験は大小問わずあると思います。その経験の先も人は生きていかなければなりません。そのとき、塀の向こうからの表現や、回復・修復を目指そうとする活動がこの社会に存在することの意味があると考えています。
このWebサイトでは、刑務所アート展の応募作品アーカイブだけでなく、「刑務所とアート」に関する国内外の事例紹介や調査研究、この領域に関わる人たちのインタビューやコラム、イベントやワークショップなどの情報を掲載していきたいと思います。ぜひ、みなさんの声も聴かせていただければ幸いです。


