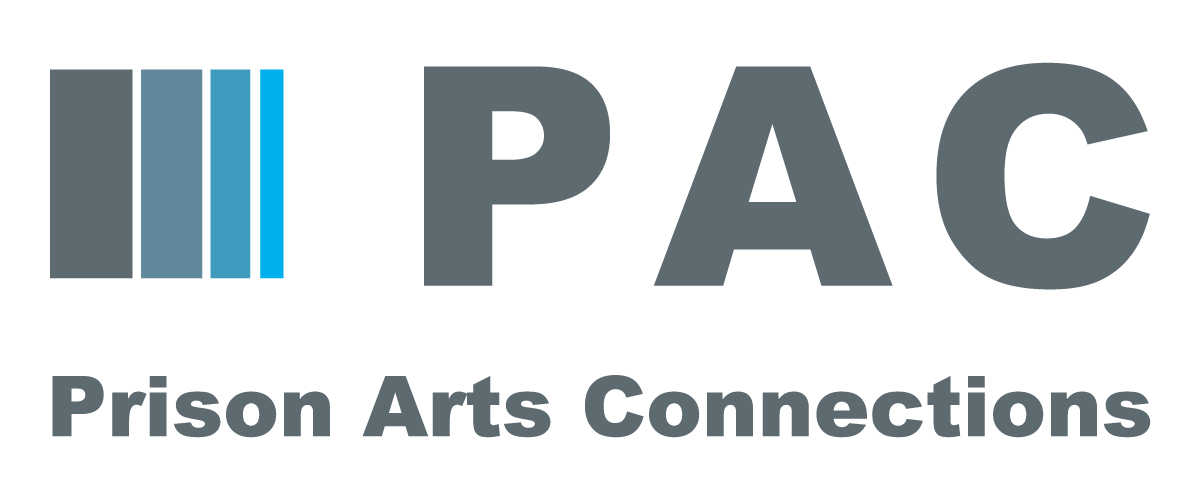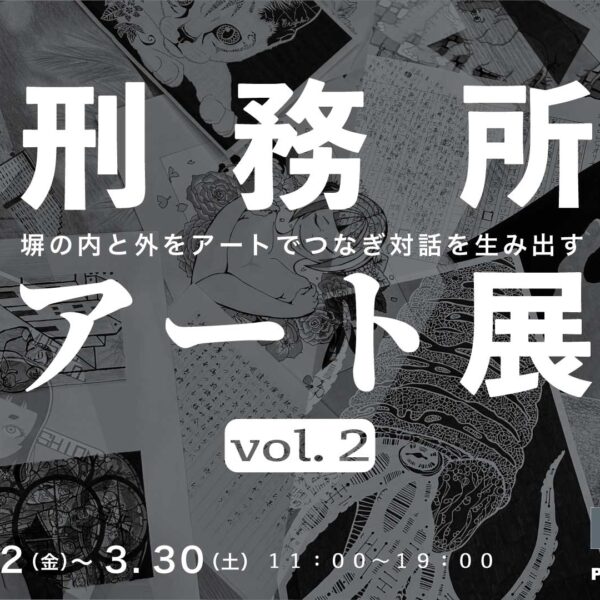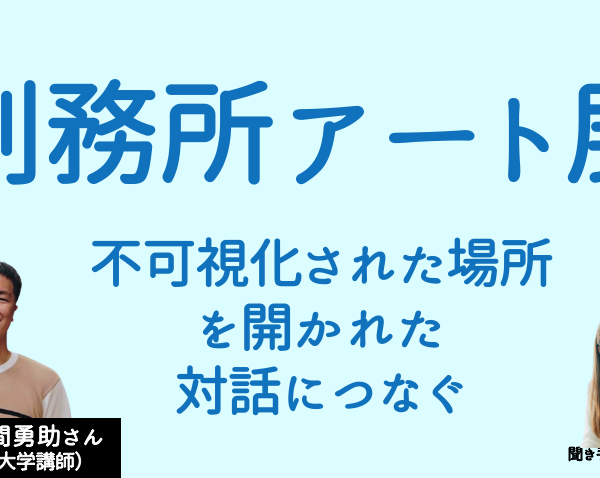8月29日に、大阪・九条にある本屋さんMoMoBooksにて原田 正治さんのお話を伺いました。原田正治さんはご自身の弟さんを殺害された被害者遺族で、加害者である長谷川敏彦さんに面会し、その対話を続けるために死刑の停止、死刑反対を訴えてきました。このトークのなかでも語られているとおり、原田さんご自身も事件をきっかけに金銭的な被害を受け、誰からの支援も受けられない孤独のなかで自暴自棄になった時期もあるなど、想像をこえる苦しみを経験されてきました。
長谷川敏彦さんは、原田さんに謝罪の手紙を送り続け、時折「絵」を送っていました。刑務所アート展では、この長谷川さんの絵を何度か展示しています。原田さんは、送られ続けてくる手紙に対して、事件から10年が経ったある時、思い立って長谷川さんと面会し、その経験を『弟を殺した彼と、僕。」(2004年、ポプラ社)に綴っています。

加害者と被害者が回復を目指して対話をするという、その修復的司法や対話が向かうところは何なのだろうか、ということにもトークのなかで触れました。被害者やその家族が、加害者に対して憎み、恨み、許せないという思いをずっと抱き続けることは大変に苦しく、人生がずっと加害者に支配されたものになってしまう。それを終わらせるために「赦し」が目指されると言われることもあるけれど、はたしてそうなのか。原田さんの言葉からは何か違う感じがある。
原田さんは長谷川さんに会った時に「ほっとした」と表現されているその感覚、「許せるようなことじゃない。いま思い出しても憎んでも憎みきれない。でも、面会を続けたい」というその感覚は、いまだ言葉にならないもののように思いました。それでも、たしかに加害者に感情をずっと奪われるような状況からは、飲めないお酒を飲み歩いてヤケになっていたような状況からは、なにか次元が変わったようなところはあるのかもしれません。
会場に来てくださったあかたちかこさんからは、会って対話することの意味は、「時間が前に進むこと」ではないだろうかと。被害者からすれば、ある日突然、自分の身に理不尽なことがふりかかり、そこで時間が止まってしまうようなところから、会って話をするというのは、そこから少しでも時間が動くことにつながるんじゃないかと。
原田さんが繰り返しおっしゃったのは、社会が「加害者像」「被害者像」を勝手につくってしまうけれど、それは違うんだということでした。加害者はこうあるべき、被害者はこういう思いでいるものだ、そんなふうに決めつけられると、原田さんが歩んだ道のようなものは見えてきません。
被害者であっても、加害者に会って話をすることができる、許せなくたって対話することに意味がある、裁判では出てこない本音が対話には出てくることがある、そんなメッセージを各所で伝える原田さんの存在は本当に大きいものであると改めて感じました。
また、長谷川敏彦さんの絵は、原田さんがお持ちのもの以外にも存在していて(長谷川さんが他の人に送っていたもの)、原田さんが初めて長谷川さんの絵を見たのは、名古屋で開かれた長谷川さんの個展だったと。展示で販売会をしていたら拘置所に注意を受けてしまったんだとか。
何度お会いしてお話を伺っても、その度に新しいことがわかってくる。またどこかで、お話の続きを伺いたいです。この貴重なお話をぜひ多くの方に聞いていただきたいです。